目次
この記事は 約5分 で読めます。
睡眠と腸内細菌の深い関係とは?
はじめに
「腸は第二の脳」。こんな言葉を耳にした事はありませんか?
腸はそう呼ばれるほど、心身の健康に深く関わっている、という意味ですが、近年の研究では、腸内細菌の状態が睡眠の質にも影響することが明らかになってきました。
つまり、腸の環境を整えることが、快眠につながる可能性があるのです。
本記事では、腸内細菌と睡眠の関係を最新研究を踏まえて解説し、日常生活でできる工夫をご紹介します!
1. 腸と脳をつなぐ「腸脳相関」
腸と脳は神経やホルモンを介して密接に連携しています。これを 「腸脳相関」 と呼びます。
● 腸内細菌がつくる物質が血液や神経を通じて脳に作用
● ストレスで腸の働きが乱れる → 眠りの質低下
● 睡眠不足 → 腸内細菌のバランス悪化
腸と睡眠は、まさに「双方向の関係」にあるのです。
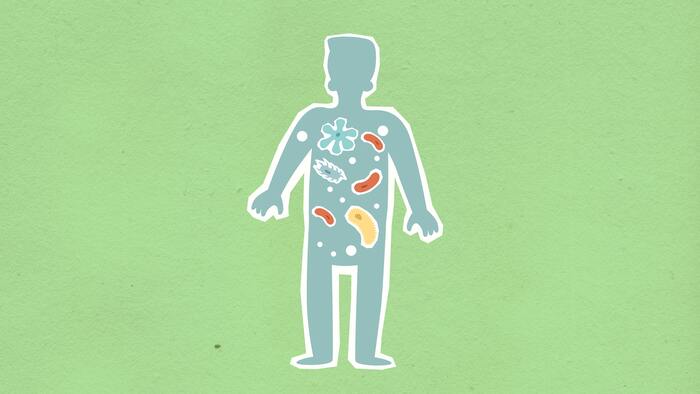
2. 腸内細菌が眠りに関わる仕組み
セロトニンとメラトニン
腸内細菌は セロトニン の生成に関わります。
セロトニンは「幸せホルモン」として気分を安定させるだけでなく、夜には「睡眠ホルモン」メラトニンに変換されます。
腸の状態が悪いとこの流れが滞り、睡眠リズムに影響を与える可能性があります。
免疫と炎症
腸内細菌は免疫系の調整にも関与します。
腸内環境が乱れると炎症性サイトカインが増え、睡眠の深さに影響することがわかっています。
3. 睡眠不足が腸内環境を乱す
逆に、睡眠不足が腸内細菌の多様性を減らすことも研究で示されています。
● 夜更かしや徹夜で善玉菌が減少
● 代謝や免疫に関わる菌が乱れ、肥満や生活習慣病リスクが増加
● 「眠れない → 腸環境悪化 → さらに眠れない」という悪循環に陥る危険
寝不足による腸内環境の悪化でこんなに色々な事が起こるんですね…。

4. 腸を整えて快眠につなげる生活習慣
それでは腸内環境を良くするにはどんな事に気をつければ良いでしょうか?
発酵食品をとる
ヨーグルト、納豆、キムチ、味噌などは善玉菌を増やし、セロトニン生成を助けます。
食物繊維を意識
野菜、果物、豆類、海藻に含まれる食物繊維は善玉菌のエサ。特に水溶性食物繊維(オートミール、バナナ)は有効です。
規則正しい生活リズム
腸内細菌にも「体内時計」があり、不規則な生活で乱れます。毎日の食事時間をそろえ、朝日を浴びることが大切です。
睡眠環境を整える
夜は照明を落とす、寝る直前のスマホを控えるといった「眠るための環境」も腸活とあわせて意識しましょう。
腸と脳、両方に優しい習慣が快眠につながるんですね!
まとめ
● 腸と脳は「腸脳相関」でつながっており、腸内細菌は睡眠リズムやホルモン分泌に関与する。
● 睡眠不足は腸内環境を乱し、さらに眠りを悪くする悪循環に陥る
● 発酵食品・食物繊維・生活リズムの調整が快眠のための腸活につながる
「よく眠れる人は腸も元気」。
腸活を取り入れることで、ぐっすり眠れる夜を手に入れましょう!
眠りを整えるためには寝具選びもとても重要です。
体に合ったマットレスや枕を使うことで、
睡眠の「質」はぐっと高まります。
当社では、“こんな眠りが欲しかった”をコンセプトに、快適な寝具をご提案しています。
ご興味のある方は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。
▶︎ グースリーマットレスで快眠体験へ
参考文献・資料
Benedict C, Vogel H, Jonas W, et al. Gut microbiota and sleep-wake regulation. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2012.
Smith RP, et al. Gut microbiome diversity is associated with sleep physiology in humans. PLoS One. 2019.
Anderson JR, Carroll I, Azcarate-Peril MA, et al. A preliminary examination of gut microbiota, sleep, and cognitive flexibility in healthy older adults. Sleep Med. 2017.
国立研究開発法人 農研機構「腸内フローラと健康」
厚生労働省 e-ヘルスネット「腸内細菌と健康」


コメント