目次
この記事は 約5分 で読めます。
寝汗が気になる?
その原因と対策を徹底解説
はじめに
朝起きたときにパジャマやシーツが汗で湿っている。そんな「寝汗」に悩まされていませんか? 寝汗は誰にでも起こるものですが、日常生活に支障をきたすほど多い場合や、原因がはっきりしない場合には注意が必要です。この記事では、寝汗の主な原因から考えられる病気、そして快適に眠るための対策までをわかりやすく解説します。
寝汗はなぜ起こるのか?
寝汗は、体温調節の一環として起こる自然な現象です。人は睡眠中に深部体温(体の内部の温度)が下がることで眠りに入りやすくなりますが、その過程で皮膚から熱を放出するために汗をかきます。 しかし、次のような原因によって、異常に多く寝汗をかくことがあります。
1. 室温や寝具の影響

部屋が暑すぎたり、布団が厚すぎたりすると、体温がこもり寝汗が増えることがあります。特に冬場は過度に暖房を入れたり、電気毛布を使い続けたりすることで寝汗がひどくなるケースがあります。
対策:
・室温は18~22℃、湿度は50~60%が理想的。
・吸湿・放湿性のある寝具を選ぶ(例:麻・綿・テンセル素材)
・通気性の良いパジャマを着用。
2. 食事やアルコールの影響

辛いものや脂っこい食事、アルコールの摂取は交感神経を刺激し、発汗を促進します。特に夕食で辛いものを食べた日は寝汗が増えるという人も。
対策:
・夕食は就寝の3時間前までに済ませる。
・アルコールの摂取は控えめにし、できればノンアルコール飲料に置き換える。
3. ストレスや自律神経の乱れ
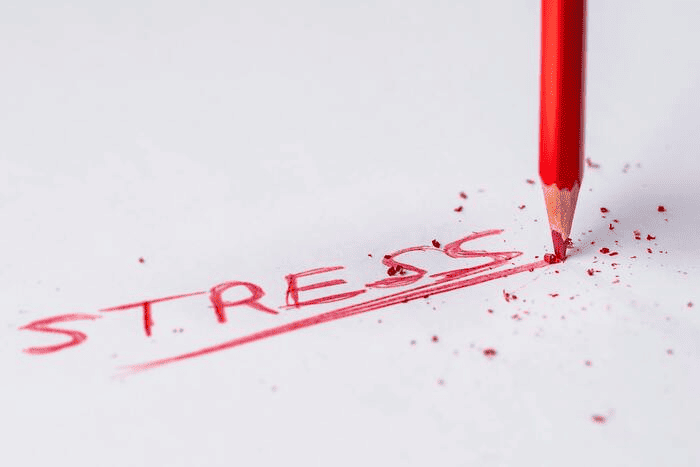
ストレスや不安感、慢性的な疲労によって交感神経が優位になり、夜間でも発汗しやすくなります。
対策:
・寝る前にスマホを見ない、明かりを暗くするなどリラックス習慣をつくる。
・軽いストレッチや深呼吸など、心身を落ち着かせる習慣を取り入れる。
4. ホルモンバランスの変化

更年期の女性に多いのが、女性ホルモン(エストロゲン)の低下による寝汗。ホットフラッシュ(突然のほてり)とともに現れることもあります。
対策:
・医師に相談し、必要であればホルモン補充療法などの選択肢も検討。
・大豆イソフラボンを含む食品(納豆、豆乳など)を日常的に取り入れる。
5. 病気が隠れていることも

まれに、寝汗は病気のサインであることもあります。以下のような症状を伴う場合は医療機関の受診をおすすめします。
注意すべき症状:
・微熱が続く、急激な体重減少
・息切れ、動悸、持続的な倦怠感
・日中も大量の汗をかく
→ 可能性のある病気:甲状腺機能亢進症、結核、悪性リンパ腫、睡眠時無呼吸症候群など
快眠のための実践的アドバイス
寝汗を軽減し、快適に眠るための具体的な工夫をご紹介します。
● 寝る前の入浴を活用
ぬるめ(38~40℃)のお湯に15分程度浸かることで、深部体温が一時的に上がり、その後の体温低下を促して寝つきやすくなります。
● 寝具をこまめに洗濯・乾燥
湿った寝具は不快感を引き起こし、睡眠の質を下げる原因に。こまめな洗濯と天日干しで快適さをキープしましょう。
● 寝室環境を見直す
遮光カーテンや静音性の高い家電を取り入れ、眠りやすい環境を整えることも大切です。
まとめ
寝汗はよくある現象ですが、生活習慣や環境を見直すことで改善できるケースがほとんどです。ただし、体調不良やほかの症状を伴う場合には早めに医療機関を受診してください。 しっかり対策をとることで、夜間の不快感を減らし、朝までぐっすり眠れるようになります。自分の体に合った方法を見つけて、より良い睡眠習慣を手に入れましょう。
また、眠りを整えるためには寝具選びもとても重要です。
体に合ったマットレスや枕を使うことで、
睡眠の「質」はぐっと高まります。
当社では、“こんな眠りが欲しかった”をコンセプトに、快適な寝具をご提案しています。
ご興味のある方は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。
▶︎ グースリーマットレスで快眠体験へ


コメント