目次
この記事は 約5分 で読めます。
中・高生の夜ふかしは仕方がない?
はじめに
「中学生になってから子どもが夜ふかしばかりで朝起きられない」「高校に入ってから遅刻しがちで心配」——そんな悩みを抱える親御さんの話をよく聞きます。
実は、中高生が夜ふかししてしまうのは 意志の弱さや怠け癖ではなく、脳の発達にともなう生理的な変化なのです。
前回のブログ年齢で変化する体内時計~ライフステージ別の睡眠リズムとその特徴でもお伝えしました通り、人間の脳はその発達段階において朝型になったり夜型になったりすることが分かってきています。
本記事では、思春期に夜型になる脳の仕組み、その結果生じるリスク、そして親ができるサポートについて解説したいと思います!
1. 思春期の脳はなぜ夜型になるのか?
体内時計のシフト
脳の成長の過程で思春期に入ると、脳内で分泌される 睡眠ホルモン「メラトニン」 の分泌タイミングが後ろにずれます。
その結果「夜になっても眠くならない」「深夜になってようやく眠気が来る」というリズムにどうしてもなってしまいます。
自制力の未発達
中高生は前頭前野(判断や自己コントロールを担う脳領域)が発達途上。
そのため「SNSを見始めたら止められない」「ゲームでつい夜更かし」という行動が出やすくなります。

2. 夜型シフトが招くリスク
とは言え、夜ふかしを繰り返す夜型生活を送っていると、以前のブログ夜ふかしは身長が伸びない?中学生が守るべき黄金の睡眠時間や、中学生のイライラ・やる気低下は睡眠不足が原因かも?親が気づくポイント、テスト前でも寝たほうがいい!中学生が知るべき睡眠の効果でもお伝えしました通り、様々な健康問題を引き起こす事が分かっています。
慢性的な睡眠不足
中高生が眠気が訪れるのは深夜なのに対して一般的な学校は朝8時半頃始業…。
必要な8〜9時間の睡眠を確保できず、慢性的な睡眠不足に陥りやすいです。
学業・集中力の低下
睡眠不足に陥った結果、学業面で記憶の定着を妨げ、注意力や集中力を低下させます。テスト前の「徹夜勉強」が逆効果なのもこのためです。
メンタル不調や不登校リスク
慢性的な睡眠不足は うつ症状や不安感、無気力と関連があり、体調不良や気分の落ち込みが続くことで 不登校や引きこもりのきっかけになるケースもが報告されています。
3. 親としてできるサポート
無理に早寝を強制すると、かえって親子関係がこじれることもあります。まずは「夜型になるのは生理的現象」、「夜ふかしは怠けではなく、脳の仕組み」と理解した上で出来ることから始めましょう
学校生活との調整
● 朝勉や朝練はできるだけ避け、朝はぎりぎりまで寝ることで睡眠時間を確保することを優先
● 必要に応じて学校や部活、習い事の指導者に相談し、柔軟に対応してもらう
光の活用
朝:起きたらすぐ朝日を浴びる(体内時計を前倒しにリセット)
夜:就寝前はスマホやPCのブルーライトを避け、照明を暖色に切り替える
短時間でも睡眠の質を高める
理想は8〜9時間ですが、難しい場合は
● 昼寝(20分程度のパワーナップ)
● 休日の寝不足リカバリー(2時間以上の寝坊は避ける)
で補いましょう。
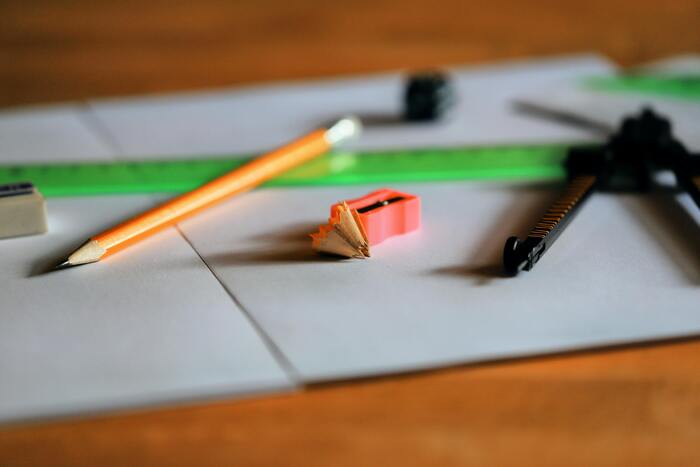
4. 将来を見据えて
思春期の夜型は一生続くわけではなく、多くは社会人になる頃には改善します。
大切なのは「今この時期をどう支えるか」。
親の理解とサポートが、子どもが心身の健康を保ちながら安心して成長するための土台になります。
まとめ
● 思春期は脳の発達上、夜型シフトが生理的に起こる
● 学校の始業時間とのずれで 睡眠不足 → 学業低下・メンタル不調・不登校リスク につながる
● 親ができることは「理解」「光の調整」「短時間の補助睡眠」「学校との調整」
夜型は一過性。あまり心配しすぎず、中高生のお子さんが少しでも睡眠を確保できる工夫と環境づくりをする事が大切なんですね!
眠りを整えるためには寝具選びもとても重要です。
体に合ったマットレスや枕を使うことで、
睡眠の「質」はぐっと高まります。
当社では、“こんな眠りが欲しかった”をコンセプトに、快適な寝具をご提案しています。
ご興味のある方は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。
▶︎ グースリーマットレスで快眠体験へ
参考文献・資料
- 年齢で変化する体内時計~ライフステージ別の睡眠リズムとその特徴~(添付資料より)
- Carskadon MA. Sleep in adolescents: the perfect storm. Pediatr Clin North Am. 2011.
- Roenneberg T, et al. A marker for the end of adolescence. Curr Biol. 2004.
- 文部科学省「子供の睡眠と生活習慣に関する調査」


コメント